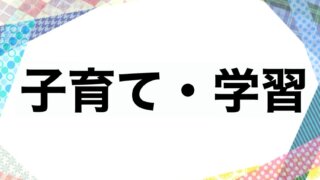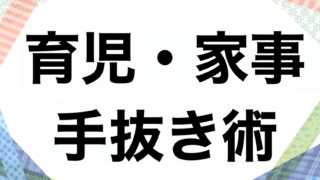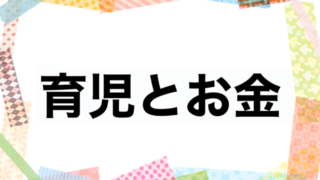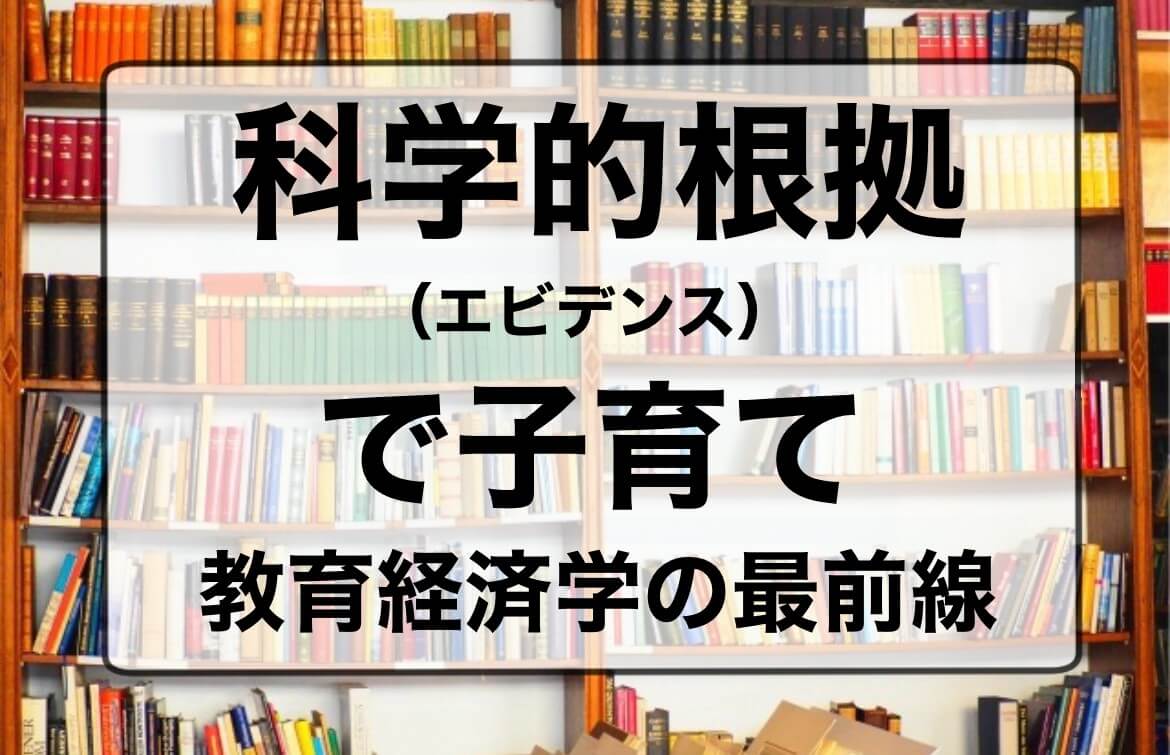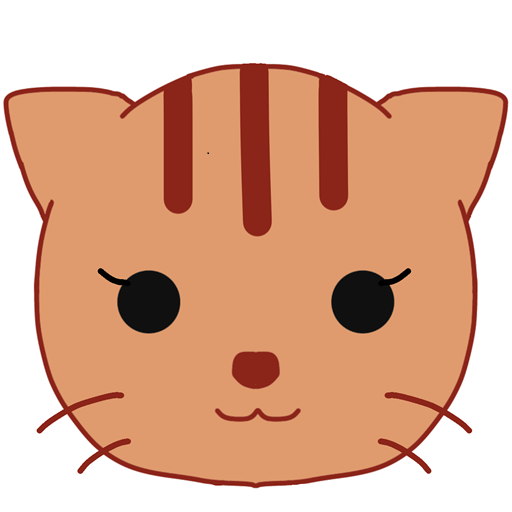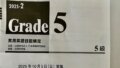こんにちは!
3人子育て日和、ブログ管理人のはなです。
現在長女10歳、長男7歳、次男4歳の育児中です。
子ども達3人を育てていくなかで、毎日の「子育ての疑問」「子育てで迷うこと」を解消すべく、さまざまな育児本を日々読みあさっています。
今回は、「科学的根拠(エビデンス)で子育て―教育経済学の最前線」著:中室牧子
について、レビューをしていきます。
この記事がおすすめの方はこんな方です。
- 「科学的根拠(エビデンス)で子育て―教育経済学の最前線」が気になっている
- 教育・子育ての研究でわかっている、さまざまな科学的根拠(エビデンス)を知りたい
- 感想や書評を知りたい
- レビューを参考にしてから、購入を検討したい
私がこの本を読んでみて、特に参考になった部分を6つご紹介していくので、「これ私も気になってた」「もっと深く知りたい」と思うことを共有できればいいなと思っています。
この本はどんな本?
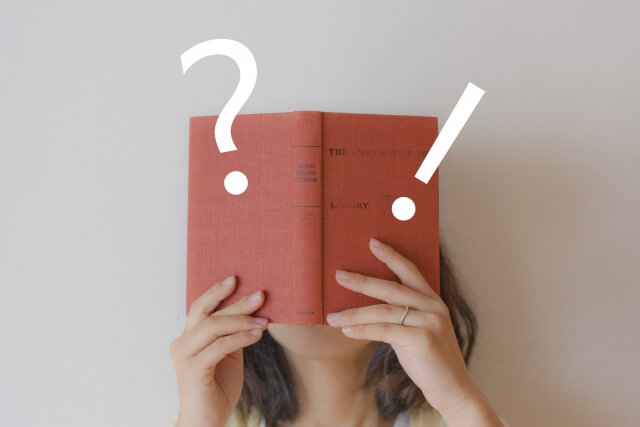
著者である、中室牧子さんは、教育経済学を専門にしている研究者です。
教育経済学者は、一人の人間を生まれた時から長期にわたって調査したものや、親・子・孫と3世代を連続で調査したものなど、さまざまなデータを駆使して教育や子育てについて分析します。
この本では、さまざまなデータを駆使して得られた科学的根拠(エビデンス)にもとづいて、教育や子育てに有益で専門的な情報を知ることができます。
子育てに成功した親の話はアテにならない

この本を読んで参考になった部分の1つ目は、「子育てに成功した親の話はアテにならない」です。
「私は○○で、子どもを有名大学に合格させました!」
「○○をして、子どもがこんな資格を取りました!」
教育や子育てに迷った時、うまくいっている人の話を聞くと「効果がある方法なんだ!真似をしたらうちの子も!」と思ってしまいますよね。
しかし、この本では、成功した親の話はアテにならないと話しています。
理由は「生存者バイアスがあるから」です。
この生存者バイアス=うまくいっている人の話ばかり聞いていると、
- まったく同じことをしていたのに失敗した人
- あまりお金や時間をかけなかったのに成功した人
このような人達の話を、知ることができないのです。

うまくいった人の話だけを聞いていると、偏った情報ばかりになってしまいそう…
失敗例やほかの成功例も知っておくと、選択の幅が広がりそうですね!
教育や子育てには、短期的な成果より長期的な成果の方が重要

参考になった部分の2つ目は、「教育や子育てには、短期的な成果より長期的な成果の方が重要」です。
短期的な成果・長期的な成果とは、それぞれどんなものかご紹介します。
短期的な成果……成績・受験
長期的な成果……社会に出てから役立つ成果
子育てをしていると、「勉強はしたの?」「遊んでばっかりいないで学習塾に行くわよ!」など、成績や受験の結果につながる勉強ばかりに目がいきがちですよね。
この本では、成績や受験は短期的な成果であり、教育や子育てには長期的な成果の方が大切であるといっているんです。
学校で学ぶ期間より、社会に出てから過ごす期間の方が圧倒的に多いため、社会に出てから役立つ成果は、たしかに大切だと感じますよね…

学校を卒業して社会に出ると、急に「勉強だけでは役に立たない」と感じることが多くなります!
では、長期的な成果=社会に出てから役に立つ成果とはどんなものなのでしょうか?
この本では、実際に企業が新卒採用で重視することの上位3つが書かれていたので、その内容をご紹介します。
- コミュニケーション能力
- 主体性
- チャレンジ精神
さらに、社会に出ると、結婚を考えることもあると思います。
では、この本に書かれていた、結婚相手に求めることの上位3つをご紹介します。
- 人柄
- 家事・育児に対する能力や姿勢
- 仕事への理解と協力
子どもが小さい頃には「テスト勉強!」「学習塾!」など、勉強のことばかり口うるさく言ってしまいがちですが、社会に出た途端、
「勉強だけでは役に立たない、コミュニケーション能力が大事」
「家事力がなくちゃいけない」
こうなると、勉強ばかり頑張ってきた子どもは「勉強だけ頑張ればいいと思っていたのに」となってしまうと思います。
親である私としては、社会に出てからの成果。つまり、
「将来高い収入を得られる」
「経済的に独立できるようになる」
このような、長期的な成果=学校を卒業したあと、社会に出てからの安定を子ども達に与えたい。と思うから、そのために勉強!勉強!と口うるさく言ってしまうと感じます。
では、長期的な成果の一つと言える
「将来高い収入を得られる」
「経済的に独立できるようになる」
これらを達成するには、どんなことをしていけばいいのでしょうか?
将来の収入を上げるために、子どもの頃にやっておくべきことベスト3

参考になった部分の3つ目は、「将来の収入を上げるために、子どもの頃にやっておくべきことベスト3」です。
経済学では、「将来の収入」は、学校を卒業したあとの教育の成果の1つだと考えます。
引用:科学的根拠(エビデンス)で子育て―教育経済学の最前線 (ダイヤモンド社)
子ども達が将来、しっかり稼ぐ力を身につけて、社会的・経済的に独立できるようになる。
これは、みなさんが教育・子育てしていくうえで、目標の中の一つにあるのではないでしょうか?
では、この本で書かれていた「将来の収入を上げるためにやっておくべきことベスト3」をご紹介します。
このベスト3には、学力や成績が入っていないことに気がつきましたか?
私は「子どもが将来、高い収入を得られるように」と思って勉強、勉強と子ども達に言っていましたが、実はやっておくべきことは勉強以外にあったんです!
「スポーツをする」「リーダーになる」をやっておくべき理由、リーダー経験をすることによってどんなことが高まるのか、それにはどんな効果があるのかが科学的根拠にもとづいて詳しく説明されています。
日常を過ごしていて、スポーツをしている・スポーツをしていた人は、活発でハキハキとした印象の方が多いと感じます。
ハキハキとしていて、リーダーシップがある方は頼りになりますよね。
結果、昇進=収入UPに繋がるのだと思いました。

このほかに、きょうだいや双子を比較した研究結果についても詳しく書かれていて、どれも興味深くてどんどん読み進めてしまいました!
非認知能力とは何なのか?

参考になった部分の4つ目は「非認知能力とは何なのか?」です。
「将来の収入を上げるためにやっておくべきことベスト3」にもあった、非認知能力を高める。
では、非認知能力とは何なのでしょうか?
非認知能力とは
この本では、「中年以降にこそ重要である」、「結婚や寿命とも関連している」、「学力を伸ばすが、その逆は起こらない」など、非認知能力がさまざまな効果をもたらす。という研究結果が詳しく書かれています。

非認知能力を身につけていれば、どんな効果が得られるのか、科学的に数値で見られるところが楽しく読み進められるポイントだと感じました!
将来の収入を上げる3つの非認知能力
非認知能力でどんな効果が得られるのか、さまざまな研究結果がこの本には書かれていますが、将来の収入との関連が明らかになっている非認知能力を3つご紹介します。
- 忍耐力
- 自制心
- やりぬく力
この3つの非認知能力を持っていると将来どんな力を発揮できるのか、また、持っていないことでどんな悪影響が起こる確率が高くなるのかについて、この本を読むことで詳しく知ることができます。
そのほかにも、将来の収入を上げるだけではなく、社会生活のさまざまな場面で有利になることがわかります。

「非認知能力はどうしたらのばせるか?」についても、科学的根拠(エビデンス)をもとに解説されています。
どんなことを経験させていけばいいのか。ヒントになるエビデンスばかりでした!
我が子には、ぜひ、3つの非認知能力を身につけて欲しいと思いました。
「第1志望のビリ」と「第2志望の1位」、どちらが有利なのか?

参考になった部分の5つ目は、『「第1志望のビリ」と「第2志望の1位」、どちらが有利なのか?』です。
「少しでも偏差値の高い学校に合格して欲しい」
こう考える親は少なくないと思います。
偏差値の高い学校に合格して欲しいと思う理由は、「周りの友人が優秀なら、自分の子も影響を受けて学力が上がる」と考えるからではないでしょうか?

私も、周りの友達が優秀なら、お互いに高め合って成績が上がるイメージを持っていました。
この疑問を解決できるヒントになるような、アメリカの空軍士官学校のデータを用いた実験内容が書かれていたので、ご紹介します。
グループ1
学力が上位層の候補生と下位層の候補生が一緒になった戦隊
グループ2
学力が中間層の候補生のみの戦隊
グループ3
完全にランダムに選ばれた候補生の戦隊(ほかの2つのグループと比較するための対象群)引用:科学的根拠(エビデンス)で子育て―教育経済学の最前線 (ダイヤモンド社)
3つのグループの中でもっとも成績が上がったのは、また、もっとも成績が上がらなかったのはどのグループなのか。
この研究結果を知ることで、「第1志望のビリ」「第2志望の1位」、どちらが有利なのかを考える、ヒントになると思います。

この研究のほかにも、小学校の学内順位がさまざまなことに影響するということをデータで表したものがあり、我が子にドンピシャな内容ばかりで、食い入るように読みましたw
別学と共学、どちらがいいのか?

参考になった部分の6つ目は、「別学と共学、どちらがいいのか?」です。
別学か共学、どちらがいいか。
正直にいうと、私は考えたことがありませんでしたw
私の地域では、共学の学校が多いので、当然我が子も共学に行くだろうと考えていたからです。
しかし、「別学と共学どちらかが我が子にとっていい選択」となると、ぜひ知りたいと思いました。
この本では別学と共学がそれぞれ何に対して有利なのか、どんな影響が起こりやすいかについて、さまざまな視点で研究された研究結果が紹介されています。
- 学力や進学
- 男子校で有利なこと、起こりやすい影響
- 女子校で有利なこと、起こりやすい影響
別学と共学のどちらかを選ぶことによって、将来の働き方や収入にはどんな影響を与えるか、結婚や出産の確率はどうなるかなども、研究結果をもとに解説されています。
別学か共学か迷っている方に、選び方のヒントになるようなおすすめの内容でした。
また、別学と共学のどちらかを選ぶことで、我が子にとって有利になること・起こりやすい影響について知りたい方にも、おすすめの内容です。

同じ学校教育や家庭環境だったとしても、男子と女子で与える影響に違いがあることを知りました。
男の子と女の子、どちらも育児している身としては、とても参考になることばかりでした。
まとめ
「科学的根拠(エビデンス)で子育て―教育経済学の最前線」で特に参考になった内容を6つご紹介しました。
この本には、今回ご紹介した6つのほかに、科学的根拠をもとに解説された教育・子育てに役立つ情報が、50個以上書かれています。
教育・子育てに役立つ情報は、ある学校の生徒全員を対象にした研究結果や、約40年かけて行われた幼児教育の効果についての研究結果など、私たち個人では到底調べられない科学的根拠をもとにした有益な情報ばかりです。
科学的根拠(エビデンス)は、とても参考になる情報ばかりではありますが、著者である中室牧子さんは、この本でエビデンスについてこう書かれています。
エビデンスは合理的な判断を助ける「補助線」にすぎない
引用:科学的根拠(エビデンス)で子育て―教育経済学の最前線 (ダイヤモンド社)
「エビデンスはいつも正しい」
ではなく、
「こんなエビデンスがあるから参考にしてみよう」
「こんなエビデンスがあるのね。うちはやらないかも」
という感じで、「何をするのか」「何をしないのか」を決めていく、参考にしていくのがいいのかなと思いました。
そして、決めていくには、まず知っておくことが大切だと思います。
この本は、科学的根拠をもとに、教育・子育てに関する有益な情報を知りたい方におすすめの内容ばかりです。
「決めるためにまず知りたい!」という方は、ぜひ、科学的根拠(エビデンス)で子育て―教育経済学の最前線を読んでみてください。