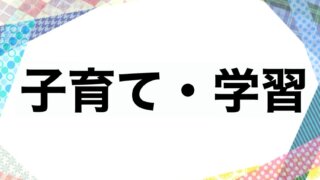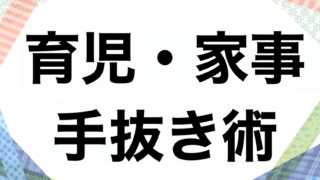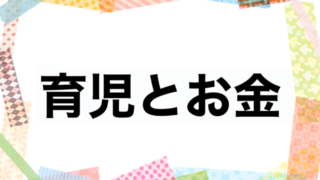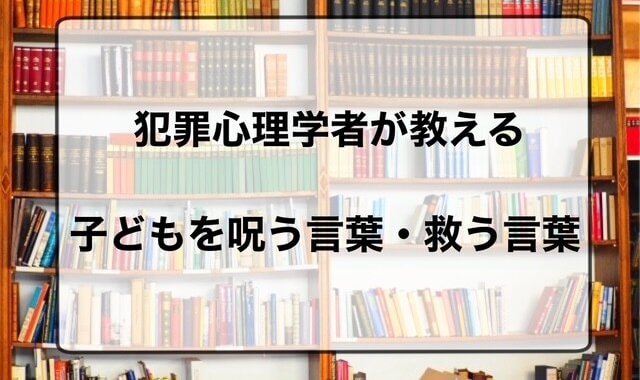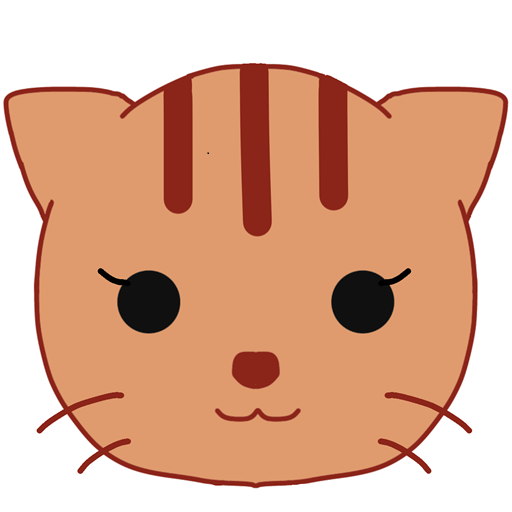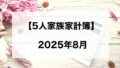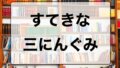こんにちは!
現在、長女9歳・長男7歳・次男4歳を育児中、はなです。
子ども達3人を育てていくなかで、毎日の「子育ての疑問」「子育てで迷うこと」を解消すべく、さまざまな育児本を日々読み漁っています。
今回は、
【犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉】著:出口保行
を読んだ感想や書評をしていきます。
- 【犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉】が気になっている。
- レビューを参考にしてから、購入を検討したい。
- 感想や書評を知りたい
こんな方におすすめの内容となっています。
ぜひ、悩みを解決できるような情報を、共有できればと思っています。
「子どもを呪う言葉」にドキリ
この本には、実際にあった事件の詳細を変えたり、いくつかの事例を組み合わせたりした、犯罪や非行の事例が載っています。
各事例の引き金となる子ども呪うの言葉が、普段私たちが子育てしている中で、よく使う言葉ばかりで少し怖くなりました。
- みんなと仲良く
- 早くしなさい
- 頑張りなさい
- 何度言ったらわかるの
- 気をつけて!
などです。
この言葉たちがどのように子どもに伝わり、どのような影響が出て非行へ向かわせるのか、犯罪や非行の事例紹介でわかります。

普段使いがちな言葉が、「大切な我が子にこんな影響を与えるものだったなんて…」と、知るいい機会になりました。
言ってしまったらどうする?

この本に書かれているような「危ない一言」を、すでに普段から言ってしまっている。
言ってしまった瞬間に「しまった!」と気づけた時の、対処法も紹介されています。
例えば、つい、いつもの調子で「何も考えないで行動するからでしょ!」と言ってしまったとします。
そんな時は、「思ったことをぱっとできるなんて、行動力があるんだね」など、フォローを忘れないようにします。
ついダメ出しをしてしまっても、リカバリーできると、フォローで個性を発揮できるいい機会になると考えることができます。
このような具体的な声掛けの仕方も説明されているので、
「危ない一言」を言ってしまってるかも…
と思っている方は、ぜひこの本を読んでみてください。

感情にまかせて、つい、言ってしまうことってありますよね。
フォローの仕方を覚えておけば、つい出てしまったダメ出しのような言葉もリカバリーできます。
修正していけばいい
どんなに立派な親でも、子育てに悩まない親はいないと思っています。
色々な育児本を読んできましたが、学校の先生でも、教育学者でも、「自分の子供に対して悩むことがある」と書かれていました。
子どもによって性格は違うし、同じ子供はいないから対処法も違う。正解がない。
子育ての正解法則がないから、色々な情報があると迷ってしまいますよね。
この本を読み進めていくうちに、「もし、子どもを責めるような言葉を言ってしまったとしても、修正していけば大丈夫」と思えるようになりました。
子育ての必勝法みたいなものはなかなか見つからないけど、良くない影響を与えるものを取り除いていくのも、いいかもしれません。

この本を読むことで、「子どもを呪う言葉」が子どもにどんな影響を与えるのか知ることができる、いい機会になったと思っています。
「子どもを救う言葉」の例が参考になる
子どもを呪う言葉がどんな非行に向かわせるのか、子どもの気持ちにどんな影響を与えるのかの解説のあとに、「子どもを救う言葉」についての解説がされています。
1万人以上の犯罪者の心理分析をし、実際に非行少年に関わってきた出口さんだからわかる、「子どもを救う言葉」の使い方が紹介されています。
使う場面、具体的な声掛けの例が解説されているので、実践しやすいな。と感じました。

この本の解説を読みながら、実際に子どもと触れ合っている場面をイメージしやすかったです。
教育方針は両親でよく話し合うことが大切

ママとパパで、意見が合わないことってよくありますよね。
例えば、
「ママは、塾に行かせたいと思っている」
「パパは、自由に友達と遊ぶ時間を取らせたい」
「ママは、子どものゲーム時間を30分にしたい」
「パパは、1時間くらいはいいと思っている」
この他にも、こんな感じの意見が合わない教育方針は、それぞれの家庭でいくつかあると思います。

細かいことを含めると、もう、たっくさん浮かびます…
両親の意見が合っていないのに、それぞれ別の教育方針で子どもに関わると、どんなことが起きるか。
この本を読んで「なるほどな。そうだよね。」と納得しました。
意見が合わないから。と諦めて、それぞれ別の教育方針で子どもに関わると、結果として子どもにどんな影響が出るのかが書かれており、ゾッとしました。

「子どものため」だと思って関わっていたことが、逆に「子どもを苦しめていた」ことに気が付けました。
まとめ
正直、この本に書かれていた「子どもを呪う言葉」を私も言ってしまっていました。
読んでいて、「なんてダメな親なんだ」と思う瞬間もありましたが、「完璧になんてできない」「修正していけばいい」と思えるようになりました。
そして、この本で紹介されている、修正するための「子どもを救う言葉」がとても参考になったと感じています。
なんでもすぐに忘れちゃう(ドリー風)私なので、定期的に何度も読み返したい本の一つになりました。
【犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉】について、レビューを見てから購入を考えたいという方の、参考になれば嬉しいです。